今日の学習内容
使用教材:【令和3年度】キタミ式イラストIT塾 ITパスポート
勉強時間:1時間
学習範囲:
Capter3-1「ファイルと文書のこと」
Capter3-2「文書をしまう場所がディレクトリ」
Capter3-3「ファイルの場所を示す方法」
Capter4-1「ハードディスクの構造と記録方法」
Capter4-2「フラグメンテーション」
Capter4-3「RAIDはハードディスクの合体技」
今日学んだ内容のポイントまとめ
Capter3-1「ファイルと文書のこと」
文書等の代表的なファイル形式には
・テキスト形式
・CSV形式
・PDF
の3種類がある。
画像用の代表的なファイル形式には
・BMP
・JPEG
・GIF
・PNG
の4種類がある。
音声用の代表的なファイル形式には
・MP3
・MIDI
の2種類がある。
動画用の代表的なファイル形式には
・MPEG
がある。
圧縮されたファイルが元に戻せる方法で圧縮することを可逆圧縮と呼び、元に戻せない方法で圧縮することを不可逆圧縮と言う。
Capter3-2「文書をしまう場所がディレクトリ」
ディレクトリとはファイルをグループ化して整理するもの
階層構造の1番上にいるディレクトリのことをルートディレクトリと言い、現在開いて作業しているディレクトリのことをカレントディレクトリと言う。カレントディレクトリから見て1階層上のディレクトリのことを親ディレクトリと言い、1階層下のディレクトリのことをサブディレクトリ(子ディレクトリ)と言う。
Capter3-3「ファイルの場所を示す方法」
ファイルまでの場所を指し示す経路のことをパスと言い、ルートディレクトからの経路を書き記す絶対パスとカレントディレクトリからの経路を書き記す相対パスと言う2種類の書き表し方がある。
パスの表記の決まり事は下記のとおり
・ルートディレクトリは「/」または「\」であらわす
・ディレクトリと次の階層との間は「/」または「\」で区切る
・カレントディレクトリは「.」であらわす。
・親ディレクトリは「..」であらわす。
Capter4-1「ハードディスクの構造と記録方法」
ハードディスクの内部には容量に応じてプラッタと呼ばれる金属製のディスクが入っている。ハードディスクはフォーマットすることでプラッタの上にデータを記録するための領域が作成される。
作成された領域の扇状に分かれた最小範囲をセクタ、そのセクタを複数集めた1周分の領域をトラックと呼ぶ。ちなみに同心円状のトラックを複数まとめると、シリンダと言う単位になる。
ハードディスクが扱う最小単位はセクタだが、OSがファイルを読み書きする時には複数のセクタを1ブロックとみなしたクラスタと言う単位を用いるのが一般的。
データへのアクセスする時間は
シーク時間+サーチ時間+データ転送時間=アクセス時間
であらわすことができる。
Capter4-2「フラグメンテーション」
ファイルの書き込みと消去を繰り返していくと、プラッタ上の空き領域は分かれて断片化してしまう。このような状態のことをフラグメンテーションと呼ぶ。フラグメンテーションが起こると、アクセス時間が長くなる。
フラグメンテーションを解消するために行う作業をデフラグメンテーション(デフラグ)と呼ぶ。デフラグは断片化したファイルのデータを連続した領域に並べ直してフラグメンテーションを解消する。
Capter4-3「RAIDはハードディスクの合体技」
RAIDは複数のハードディスクを組み合わせることおでハードディスクの速度や信頼性を向上させること。
RAIDはRAID0~RAID6までの7種類あり、高速化を実現するRAID0と信頼性を高めるRAID1、そしてRAID5が一般的に使われている。
RAID0(ストライピング)はひとつのデータを2台以上のディスクに分散させて書き込みを行う。分散させて書くため高速化がはかれる反面、いずれか1台でも故障すると全ファイルが失われてしまうため信頼性は低い。
RAID1(ミラーリング)は2台以上のディスクに対して常に同じデータの書き込みを行う。使えるディスク領域は半分以下になるが、常にバックアップがある状態のため、信頼性は高い。
RAID53台以上のディスクを使って、データと同時にパリティと呼ばれる誤り訂正符号も分散させて書き込みをおこなう。いずれか1台が故障しても、他のディスクにあるパリティ情報を使ってデータを復元できるため信頼性は高い。
感想・気づき・つまづいた点
Chapter4に関しては、大半がハードディスクに関する説明が入っていました。令和3年版を読んでいるため、当時はハードディスクがまだ全盛期だったため、ハードディスクに関する問題がたくさん出たかもしれませんが、現在はSSDが主流であり、「いちばんやさしいITパスポート」では、ハードディスクに関する記述は、ほとんどなく、SSDの特徴ばかりがあったので、私と同じように古い本を読んでいる方は、気をつけましょう。
ただ、ハードディスクの仕組みとか、なぜ使用年数が増えると起動やアクセス時間が掛かるようになるのかが、わかったので、非常に勉強になりました。長年の疑問が解決して、非常にスッキリした気分になりました。
明日の予定
今日はChapter3ファイルとディレクトリ~Chapter4ハードディスクまでが終了し、予定通りChapter3と4が全て終了しました!
明日からはChapter5に突入します。
明日もできればChapter5OSとアプリケーション~Chapter6表計算ソフトのChapter2つ分を終わらせたいと思います。
ITパスポート試験まで残り15日。
明日も勉強がんばります。

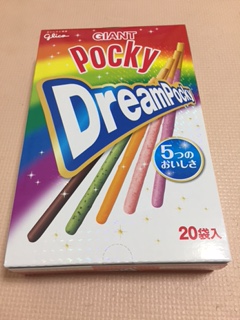
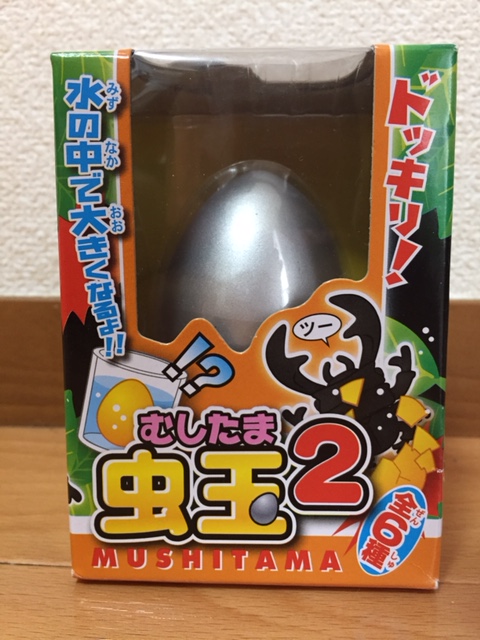









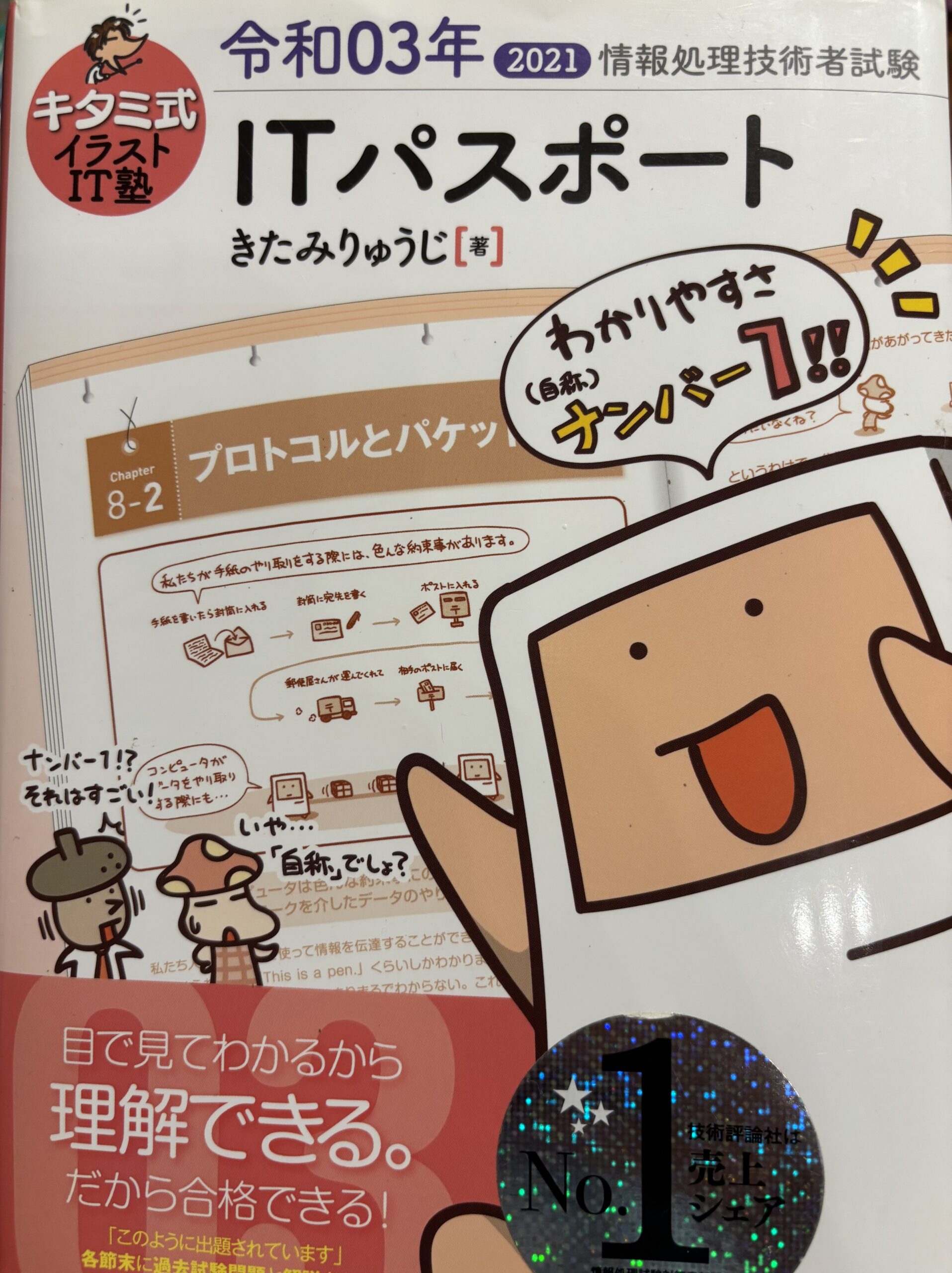

コメント