今日の学習内容
使用教材:【令和7年度】 いちばんやさしい ITパスポート 絶対合格の教科書+出る順問題集 (絶対合格の教科書シリーズ)
勉強時間:1時間
学習範囲:
Lesson11-01「コンピュータの種類」
Lesson11-02「コンピュータの5つの役割」
Lesson11-03「演算と制御」
Lesson11-04「記憶」
Lesson11-05「入力と出力」
Lesson11-06「入出力インターフェース」
出る順!過去問&完全解説
今日学んだ内容のポイントまとめ
Lesson11-01「コンピュータの種類」
コンピュータを区別する境界線が曖昧になってきており、現在の基準は、「大きさ」と「処理能力」くらいしかない。基本的に大きければ大きいほど処理能力が高いコンピュータになる。
コンピュータの種類
・マイクロコンピュータ
・ウェアラブル端末
・携帯情報端末
・タブレット端末
・PC(パソコン)
・サーバ
・ブレードサーバ
・汎用コンピュータ
・スーパーコンピュータ
等
Lesson11-02「コンピュータの5つの役割」
コンピュータの各装置の役割は「演算」「制御」「記憶」「入力」「出力」の5種類に分類することができる。
Lesson11-03「演算と制御」
コンピュータの5つの役割のうち「演算」と「制御」はともに「CPU」が担っている。CPUはプロセッサと呼ばれることもある。
CPUの性能は
・クロック周波数
・コア
・レジスタのデータサイズ
の3つの指標で表される。
クロック周波数とはCPUが動く速さを表す指標で、CPU内にある発振器が1秒間に発生させる信号の回数のこと。クロック周波数の単位はHz(ヘルツ)で表す。ITパスポート試験では、CPUの処理能力を計算する問題が出題される。
コアとはCPU内にある演算(計算)処理を行う装置のこと。複数のコアを持つCPUのことをマルチプロセッサと言い、2つのコアを持つプロセッサをデュアルコアプロセッサ、4つのコアを持つプロセッサをクアッドコアプロセッサと言う。マルチプロセッサでは、それぞれのコアば別々の処理を実行できるため、多くのコアが搭載されているCPUの方が性能が高い。
レジスタとは、CPU内にあるデータを一時的に記憶する装置のこと。レジスタのデータサイズは主に32ビット、64ビットの2種類があり、64ビットCPUの方が一度に読み込むことができるデータが大きいので、より高速に処理をすることができる。
Lesson11-04「記憶」
記憶装置とは、その名のとおりデータを記憶する装置のこと。コンピュータに搭載されている記憶装置は大きく次の3つに分類することができる。
・主記憶装置
・補助記憶装置
・キャッシュメモリ
主記憶装置とはCPUが直接読み書きをする記憶装置のこと。主記憶やメインメモリと呼ばれることもある。主記憶装置には、1.データを高速に出し入れできる、2.保存されたデータはコンピュータの電源を切ると消滅する、といった特徴がある。
補助記憶装置とは、主記憶装置を補助するための記憶装置のこと。データを長期的に保存することが主な役割で主記憶装置と違い、電源を切ってもデータが消えない。代表的な補助記憶装置にはHDDやSSDがある。
SSDには1.機械的に動く可動部品がないため振動や衝撃に強い、2.消費電力が少ない、と言った特徴があり、HDDに代替するものとして期待されている。
キャッシュメモリとはCPU内部に搭載されている超高速の記憶装置のこと。主記憶装置の処理速度の差を埋めるために使われる。
半導体メモリとは半導体に電気を通すことでデータを保存する装置のこと。半導体メモリのうち、ITパスポート試験では、RAMとROMの違い、DRAMとSRAMの違い、フラッシュメモリの概要が主題されやすい。
RAMとは電源が切れるとデータが消滅してしまうメモリ(揮発性メモリ)のこと。代表例は主記憶装置やキャッシュメモリなど。
ROMとは電源を切っても保存されるメモリ(不揮発性メモリ)のこと。代表例はSSDやUSBメモリなど。
DRAMとは絶えずリフレッシュを繰り返し続けているRAMのこと。リフレッシュとはデータが消えないように1秒間に何度も繰り返し電荷を食われうこと。DRAMは主に主記憶装置として使われている。
SRAMとはリフレッシュをする必要がないRAMのこと。主にキャッシュメモリとして使われている。
フラッシュメモリとは電気的にデータを書き換えができるROMのこと。代表例はSSD、USBメモリ、SDカード等。
Lesson11-05「入力と出力」
入力装置とはコンピュータにデータを入力するための装置のこと。代表例はキーボード、マウス、タッチパネル、ペンタブレット、スキャナー等。
出力装置とは、コンピュータの処理結果を表示するための装置のこと。代表例はディスプレイ、プリンター等。
ディスプレイとはコンピュータが処理した結果などを表示する装置のこと。ディスプレイは人間の目では識別できないほど細かいマスで区切られており、そのマスを赤、緑、青(光の三原色、RGB)で塗りつぶすことで、文字や画像を表現する。
dpiとは1インチあたりのドットの数を表す単位で、dpiの数値が多いほど、よりきれいな画像等の入出力ができる。dpiを単位とするプリンターやスキャナーなどの性能の尺度を「解像度」と言う。
ppmとは、プリンターが1分間に印刷できるページ数を表す単位のこと。数値が多いほど、高速で印刷することができる。
Lesson11-06「入出力インターフェース」
入出力インターフェースとはある機器と機器をつなぐ際に使用するケーブルの接続口の形状やデータをやり取りする方式のこと。
USBとはキーボードやマウスなどの周辺機器を接続できる現在最も普及している入出力インターフェース。USBにはバスパワーと言う機能があり、ケーブルを通して周辺装置に電力を送ることができる。
HDMIとは、映像や音声をやり取りする規格のこと。1本のHDMIケーブルで映像と音声の両方を一度にやり取りすることができる。
Bluetoothとは、近距離間(数m)でデータをやり取りする無線インターフェースの規格のこと。
デバイスドライバとはPCから周辺機器を操作するためのソフトウェアのこと。プリンターやスキャナーなどを購入した際に同梱されているCD-ROMに入っており、インストールすることでプリンターを利用することができるようになる。
プラグアンドプレイとは、周辺機器をPCに接続した際に、自動的にデバイスドライバをインストールと設定を行う機能のこと。
出る順!過去問&完全解説
13問中13問正解
感想・気づき・つまづいた点
第11章ハードウェアの内容は、ほとんど聞いたことのある、もしくは実際に体験したことのある内容ばかりだったので、比較的学びやすい内容でした。
DRAMとかSRAMあたりが初耳の用語なので、このあたりの用語だけ注意していれば、基本的には点が取りやすい範囲なのでは?と感じました。
明日の予定
今日は予定通り第11章ハードウェアを終了することができました。
明日からは第12章ソフトウェアに取り掛かります。
明日の目標はLesson12-01「OSの機能」~Lesson12-05「情報デザインとソフトウェアの権利」を学んで
第12章を終わらせたいと思います。
第11章ハードウェアの内容は基本的に仕事でパソコンを使っていたら、自然と聞く内容のものが多かったので、恐らく
第12章ソフトウェアの内容も学びやすい内容なんじゃないかな?と期待をしております。
と言うことで、明日も勉強がんばります。
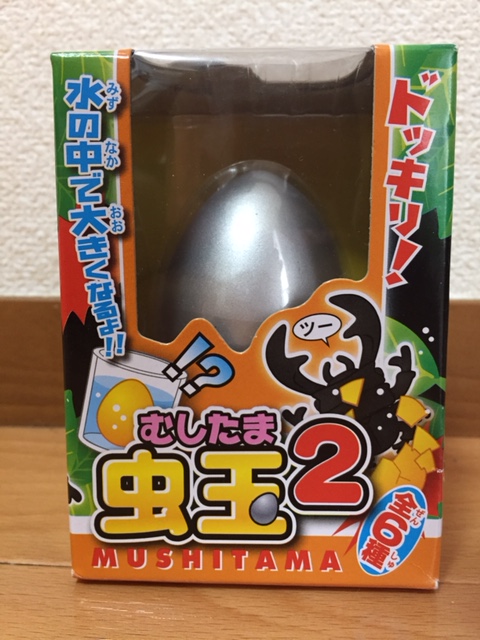










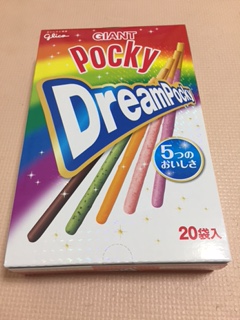
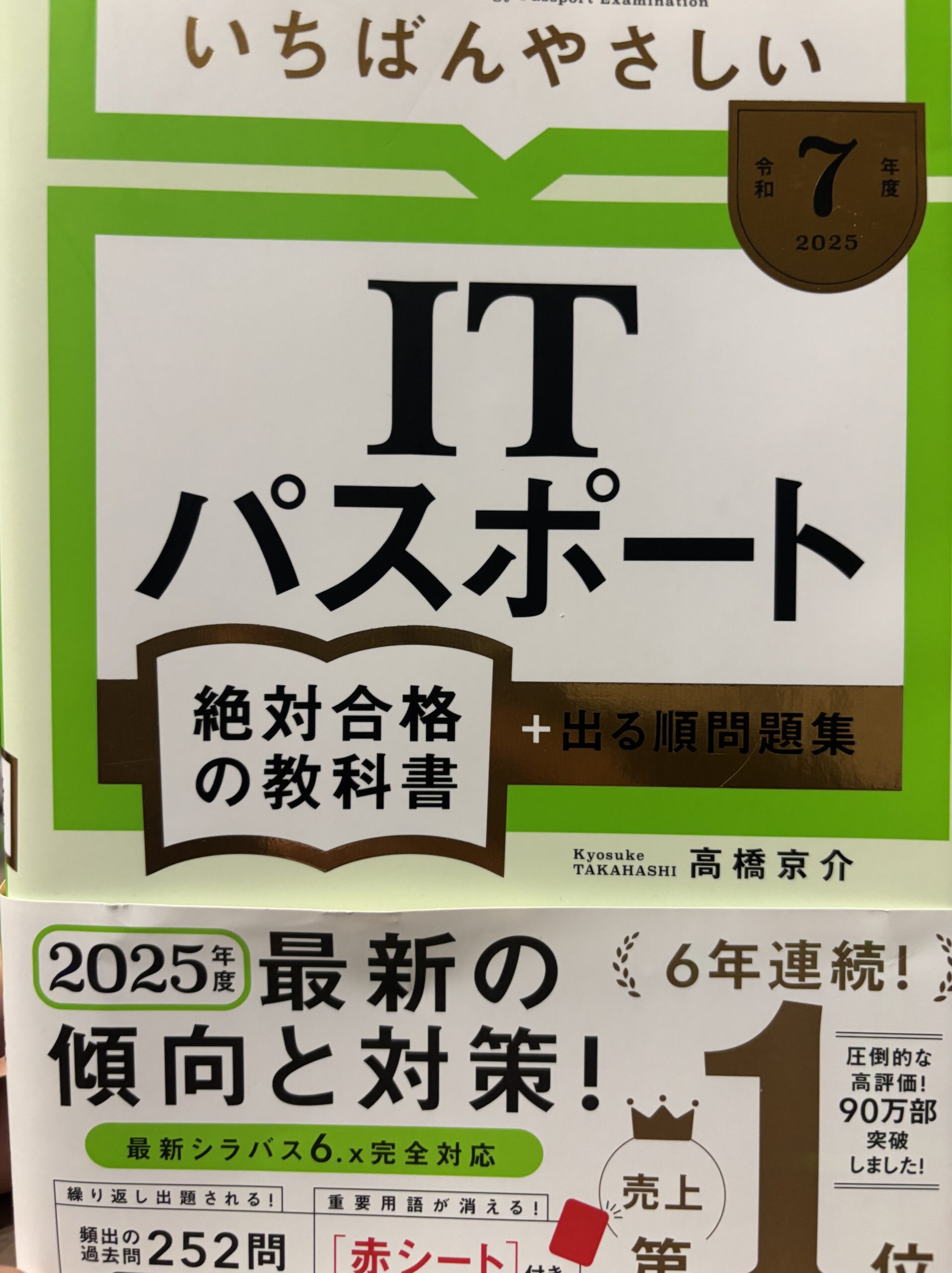

コメント