今日の学習内容
使用教材:【令和3年度】キタミ式イラストIT塾 ITパスポート
勉強時間:1時間30分
学習範囲:
Capter8-1「LANとWAN」
Capter8-2「プロトコルとパケット」
Capter8-3「ネットワークを構成する装置」
Capter8-4「TCP/IPを使ったネットワーク」
Capter8-5「ネットワーク上のサービス」
Capter8-6「WWW(World Wide Web)」
Capter8-7「電子メール」
今日学んだ内容のポイントまとめ
Capter8-1「LANとWAN」
事業所や家など、狭い範囲のネットワークをLAN、LAN同士をつなぐ広域のネットワークをWANと呼ぶ。
専用回線方式とはパソコンとパソコンを直接1本の回線で結ぶ方法。専用回線方式では、1対1の通信しかできない。
回線交換方式とは送信元から送信先に至る経路を交換機がつなぎ、通信路として固定する方法。複数のパソコンをつなぐことはできるが、回線使用中は回線が占有されるため、他の端末が、その回線を使うことはできなくなる。アナログ電話の通信路。
パケット交換方式とは、パケット(小包)という単位に分割された通信データを交換機が適切な回線へと送る方法。複数の端末で回線を共有して使うことができることから、現在のコンピュータ・ネットワークでは用いられるのは基本的にすべてパケット交換方式。
LANの接続携帯のことをトポロジーと呼び、代表的なトポロジーは
・スター型
・バス型
・リング型
の3種類。
LANの規格として、現在最も普及しているのがイーサネット。イーサネットはアクセス制御方式としてCSMA/CD方式を採用している。
CSMA/CD方式とは、ネットワーク上の通信状況を監視して、送信を行っている者がいないか確認をしてからデータの送信を開始し、それでも同時に送信してしまい、通信パケットが衝突した場合は、ランダムに求めた時間分待機してから再度送信する方式。この方法により1本のケーブルを複数のコンピュータで共有することが可能になる。
ネットワークの処理形態の代表的なものは
・集中処理
・分散処理
・クライアントサーバシステム
の3種類。集中処理と分散処理のいいとこ取りしたクライアントサーバシステムが現在の主流。
Capter8-2「プロトコルとパケット」
プロトコルとはネットワークを通じてコンピュータ同士がやり取りするためのルール。
プロトコルには様々な種類があり、
・第7層アプリケーション層
・第6層プレゼンテーション層
・第5層セッション層
・第4層トランスポート層
・第3層ネットワーク層
・第2層データリンク層
・第1層物理層
と、上記のとおり7階層にわけたものをOSI基本参照モデルと言う。
インターネットの世界で標準とされているTCP/IPというプロトコルを使うネットワークでは、通信データをパケットに分割して通信を行う。通信路上に流せるデータ量は有限であり、まとめて大量のデータを流すと、その間、誰もネットワークを利用できなくなるため、パケットに分割する方法をとっている。
Capter8-3「ネットワークを構成する装置」
NICとはコンピュータをネットワークに接続するための拡張カードのこと。LANボードとも呼ぶ。NICをはじめとするネットワーク機器には製造段階でMACアドレスと言う番号が振り分けられており、イーサネットでは、このMACアドレスを使って各機器を識別している。
リピータとは第1層物理層の中継機能を提供する装置のこと。リピータを間に挟むことで、遠くまで通信することができるようになる。
ブリッジは第2層データリンク層の中継機能を提供する装置のこと。セグメント間の中継約として、流れてきたパケットのMACアドレス情報を確認し、必要であれば他方のセグメントへとパケットを流す。
セグメントとは、無条件にデータが流される範囲(論理的に1本のケーブルでつながっている範囲)のこと。
ハブとはLANケーブルの接続口(ポート)を複数持つ集線装置のこと。ハブには内部的にリピータを複数束ねたものであるリピータハブと、ブリッジを複数束ねたものであるスイッチングハブの2種類がある。
ルータとは、第3層ネットワーク層の中継機能を提供する装置のこと。異なるネットワーク同士の中継役として、流れてきたパケットのIPアドレス情報を確認したあとに、最適な経路へとパケットを転送する。
ゲートウェイとは第4層トランスポート層以上が異なるネットワーク間でプロトコル変換による中継機能を提供する装置のこと。
Capter8-4「TCP/IPを使ったネットワーク」
TCPとはネットワーク上で正しくデータが送られたことを保証する仕組みを定めたもの。
IPとは複数のネットワークをつないで、その上をパケットが流れる仕組みを定めたもの。
TCPとIPとはを組み合わせた仕組みのことをTCP/IPと言う。
TCP/IPのネットワークにつながれているコンピュータやネットワーク機器は、IPアドレスで管理されている。
IPアドレスはグローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスの2種類ある。
グローバルIPアドレスとはインターネットの世界で使用するIPアドレスのことで、民間の非営利機関によって世界中で一意に割り当てられている。
プライベートIPアドレスとは、LANの中で使えるIPアドレスのことで、LAN内で重複がなければシステム管理者が自由に割り当てることができる。
IPアドレスの内容はネットワークアドレス部(どのネットワークか)とホストアドレス部(どのコンピュータか)とに分かれている。
IPアドレスは使用するネットワークの規模によってクラスA、クラスB、クラスCの3つのクラスに分けられており、クラスによって32ビットの中の何ビットをネットワークアドレス部に割り振るかが決められている。
サブネットマスクとはIPアドレスの32ビット中、ネットワークアドレス部を増やすことで、ネットワークを事業部事等に分割できるようにすること。
DHCPとはIPアドレスアドレスの割当を自動化すること。
NATとはグローバルIPアドレスとプライベートIPアドレスとを1対1で結びつけて、相互に変換を行うこと。
IPマスカレードとはグローバルIPアドレスと複数のプライベートIPアドレスを結びつけて、1対複数の変換を行うこと。
DNSとはドメイン名とIPアドレスを関連付けて、相互に変換する仕組みのこと。
Capter8-5「ネットワーク上のサービス」
ネットワーク上の代表的なサービス
| HTTP | Webページの転送に利用するプロトコル |
| FTP | ファイル転送サービスに利用するプロトコル |
| Telnet | 他のコンピュータにログインして、遠隔操作を行う際に使うプロトコル |
| SMTP | 電子メールの配送部分を担当するプロトコル |
| POP | 電子メールの受信部分を担当するプロトコル |
| NTP | コンピュータの時刻合わせを行うプロトコル |
ネットワークサービスはポート番号により、識別する。そのため、IPアドレスとポート番号は常に1セット。
Capter8-6「WWW(World Wide Web)」
WWWとはインターネットで標準的に使われているドキュメントシステムのこと。利用するにはWebサーバとWebブラウザが必要。
URLとはWeb上で取得したいファイルの場所を指し示すもの。
Capter8-7「電子メール」
メールの宛先は
・TO:本来の宛先
・CC:参考用に送る宛先
・BCC:他の人には見えない状態で参考用に送る宛先
の3種類。
SMTPとは電子メールを送信するプロトコル。
POPとは電子メールを受信するプロトコル。
IMAPとは電子メールを受信するプロトコル。POPとの違いは、送受信データをサーバ上で管理するため、どのコンピュータからも同じデータを参照することができる。
電子メールはMIMEという規格の登場により、画像データなどのファイルの添付ができるようになった。
感想・気づき・つまづいた点
毎日のようにインターネットは使っているので、URLとかHTMLとかは、横文字でも比較的聞き慣れているからか、わかりやすい部分もたくさんあるんですけど、OSI基本構想モデルとか、ネットワークアドレス部みたいな、ネットワークの仕組みの話になると、急にイメージがわかず、チンプンカンになるので、理解できているのか、理解できていないのか、判断が非常に難しい範囲ですね。
過去問で理解度を確認しましたが「これが答えだ!」と明確に判断できるわけではなく、でも何となくこれかな?と選んだ回答が正解だったりしたので、本当に理解度がわからない範囲でした。テスト直前にもう一度復習したいと思います。
明日の予定
今日はボリュームたっぷりのChapter8ネットワークが無事に終了しました!
明日からはChapter9セキュリティに突入します。
明日の目標はChapter9-1ネットワークに潜む脅威~Chapter9-5暗号技術とディジタル署名を終わらせたいと思います。
ITパスポート試験まで残り12日。
明日も勉強がんばります。



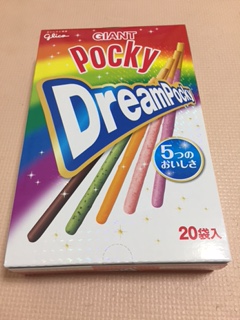





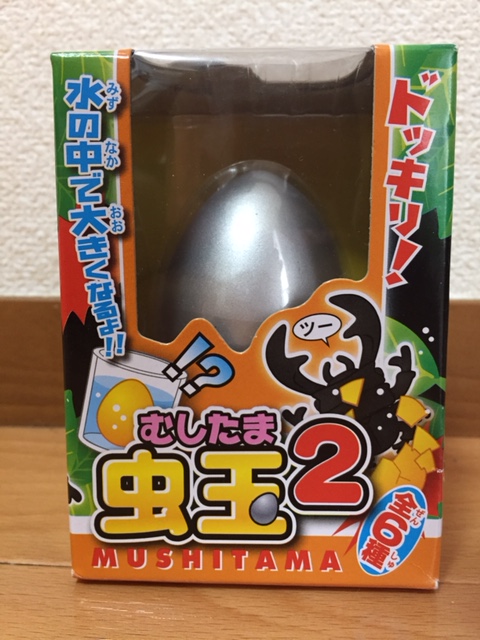


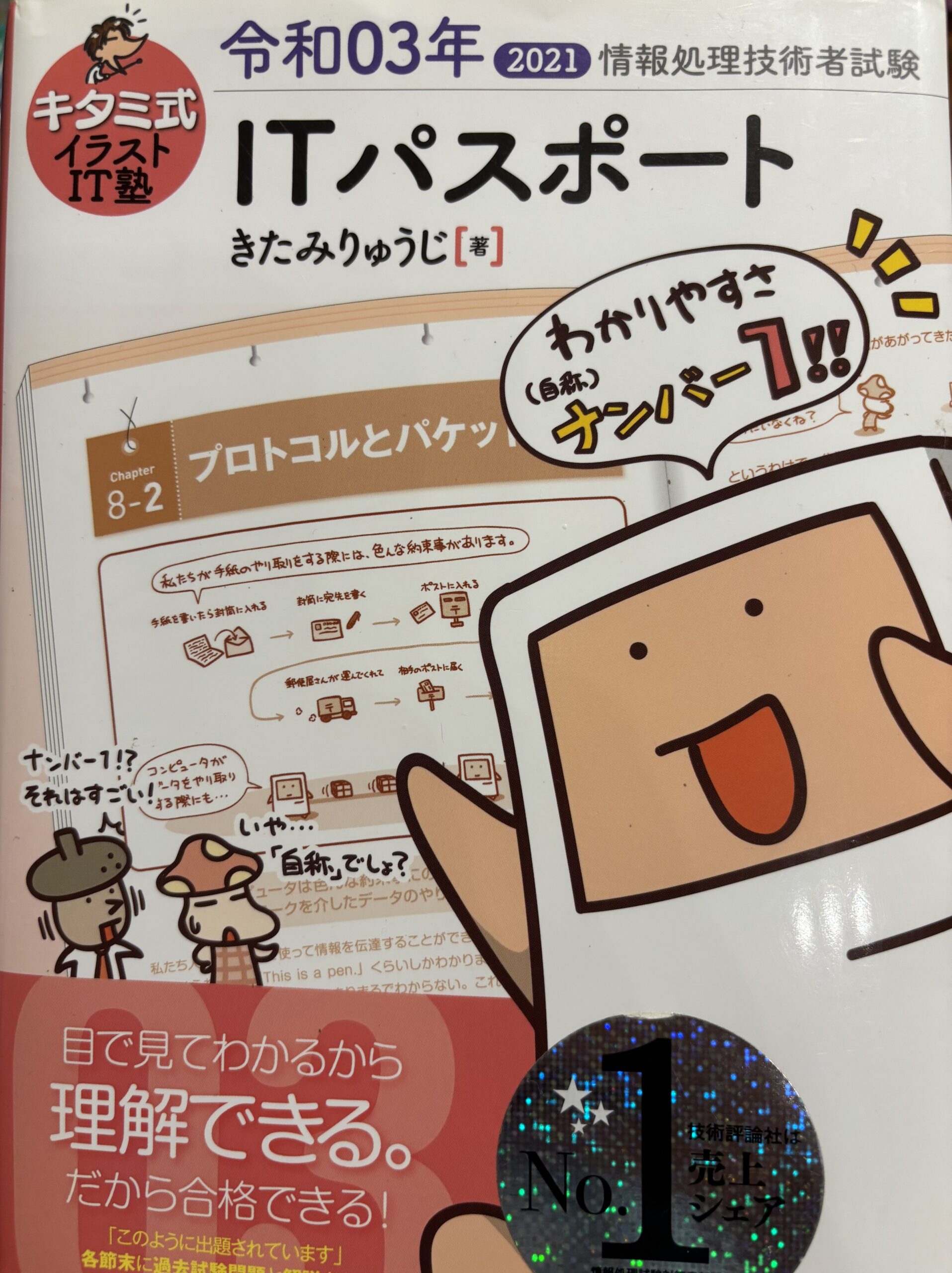

コメント