今日の学習内容
使用教材:【令和3年度】キタミ式イラストIT塾 ITパスポート
勉強時間:45分間
学習範囲:
Capter12-1「プログラミング言語とは」
Capter12-2「構造化プログラム」
Capter12-3「変数は入れ物として使う箱」
Capter12-4「アルゴリズムとフローチャート」
Capter12-5「代表的なアルゴリズム」
Capter12-6「データの持ち方」
今日学んだ内容のポイントまとめ
Capter12-1「プログラミング言語とは」
プログラミング言語とはコンピュータに作業指示を伝えるための言葉。代表的なプログラミング言語にはC言語、BASIC、COBOL、Java等がある。
プログラミング言語で書いたソースコードを機械語に翻訳する方法としてインタプリタ方式とコンパイラ方式がある。
インタプリタ方式とはソースコードに書かれた命令を1つずつ機械語に翻訳しながら実行する方法。動作を確認しながら作れるが、実行速度は遅くなる。
コンパイラ方式とはソースコードの内容を最初にすべて翻訳して機械語のプログラムを作成する方法。作成途中では動作確認ができないが、高速で動かせる。
Capter12-2「構造化プログラム」
構造化プログラミングとは、プログラムを機能単位の部品に分けて、その組み合わせによって全体を形作る考え方のこと。
構造化プログラミングでは、原則的に順次構造、選択構造、繰返し構造の3つの制御構造だけでプログラミングを行う。
Capter12-3「変数は入れ物として使う箱」
変数とは、数字や文字列を入れることができる箱のようなもの。変数を使うことで、仮の名前や数字でプログラミングをすることができる。
Capter12-4「アルゴリズムとフローチャート」
アルゴリズムとは、処理する手順のこと。そして、このアルゴリズムをわかりやすく記述するために用いられるのがフローチャート(流れ図)。
Capter12-5「代表的なアルゴリズム」
探索は箱の中から特定のデータを見つけるアルゴリズム。有名なアルゴリズムは二分探索法。
整列は箱の中から特定のデータを並べ替えるアルゴリズム。有名なアルゴリズムはバブルソート。
Capter12-6「データの持ち方」
データを配置する方法をデータ構造と呼ぶ。
データ構造の代表的なものは
・配列
・リスト
・木(ツリー)構造
・キュー
・スタック
の5種類。
感想・気づき・つまづいた点
プログラミングは暗記が必要なものは少なく、計算問題のような多いので、本番で点が取れるかどうかは微妙なところです。
いちばんやさしいITパスポートでも、必ず出題されると書かれていたため、対策は必須なんだと思いますが、同じくいちばんやさしいITパスポートにプログラミングの問題は後回しに必ずすることと書いてあったため、ある意味、捨てても良いところなのかもしれません。
とりあえず一度テキストを見た直後に解いたら、時間は掛かりますが、一応は解けたので、プログラミングを捨てることはせず、他の問題を急いで解いて、プログラミングの問題に時間を割けられるように頑張りたいと思います。
明日の予定
今日はChapter12プログラムの作り方が無事に終了しました!
明日からはChapter13システム構成と故障対策に突入します。
明日の目標はChapter13-1コンピュータを動かせるカタチの話~Chapter13-5転ばぬ先のバックアップを終わらせたいと思います。
ITパスポート試験まで残り7日。
明日も勉強がんばります。



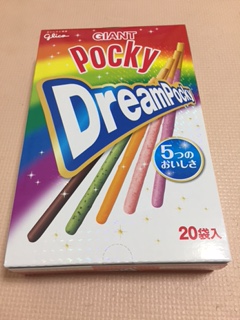






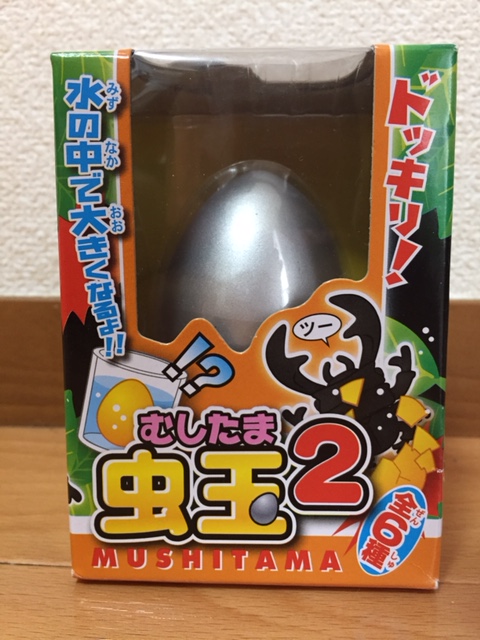

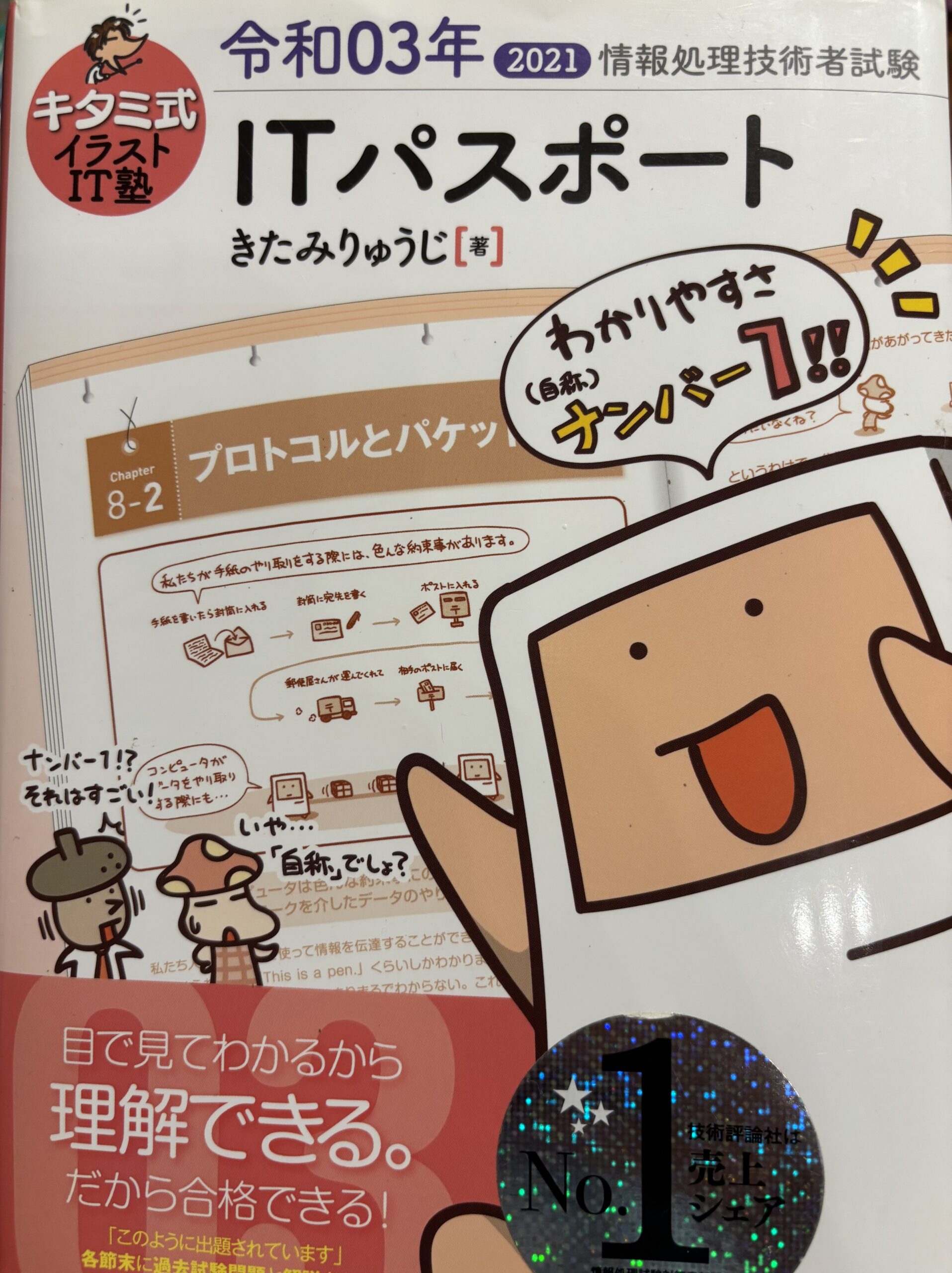

コメント