今日の学習内容
使用教材:【令和3年度】キタミ式イラストIT塾 ITパスポート
勉強時間:45分間
学習範囲:
Capter14-1「企業活動と組織のカタチ」
Capter14-2「電子商取引(EC)」
Capter14-3「経営戦略と自社のポジショニング」
Capter14-4「外部企業による労働力の提供」
Capter14-5「関連法規いろいろ」
今日学んだ内容のポイントまとめ
Capter14-1「企業活動と組織のカタチ」
代表的な組織形態は職能別組織、事業部制組織、プロジェクト組織、マトリックス組織の4種類。
職能別組織とは、職能によって部門分けする組織構成。
事業部制組織とは、取り扱う製品や市場ごとに独立性を持った事業部を設ける組織構成。事業部単位で必要な職能部門をもつため、各々が独立して経営活動を行える。
プロジェクト組織とは、各部門から必要な人材を選抜して適宜チーム編成を行う組織構成。期間限定などのキーワードが出てきたらプロジェクト組織。
マトリックス組織とは、事業部と職能別など、2系統の所属をマス目状に組み合わせた組織構成。2系統などのキーワードが出てきたらマトリックス組織。
ITパスポート試験では、事例を挙げて、どの組織構成に該当するかを問われる問題が出題される。
CEOとは最高経営責任者のこと。
CIOとは最高情報責任者のこと。IはInfomationの略と分かれば情報の役員であることがわかる。
Capter14-2「電子商取引(EC)」
ネットワークなどを用いた電子的な商取引のことをECと呼ぶ。
取引の形態は誰と誰が取引するかによって、様々な形態がある。
この場合に出てくる登場人物はB(企業)、C(個人)、G(政府)、(E)従業員。
・B to B:企業間の取引
・B to C:企業と個人の取引
・C to C:個人間の取引
・B to E:企業と社員の取引
・G to B:政府や自治体と企業間の取引
・G to C:政府や自治体と個人間の取引
EDIとは電子データ交換と訳され、交換されるデータ形式の統一化や機密保持など、ECを円滑に行うための仕組みのことを指す。
EDIに必要な取り決めとして、情報伝達規約、情報表現規約、業務運用規約、取引基本規約の4階層が定められている。
Capter14-3「経営戦略と自社のポジショニング」
SWOT分析とは自社の現状を強み、弱み、機会、脅威という4つの要素に分けて整理することで、自社を取り巻く環境を分析する手法のこと。
プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)とは縦軸に市場成長率、横軸に市場占有率をとり、自社の製品やサービスを花形、金のなる木、問題児、負け犬という4つに分類して、資源配分の検討を行う手法のこと。
コアコンピタンスとは、他社には真似できない、企業独自のノウハウや技術などの強みのこと。
ベンチマーキングとは、最強の競合相手または先進企業と自社を比較することで、製品、サービス、および実践方法を定性的・定量的に測定すること。
Capter14-4「外部企業による労働力の提供」
外部企業による労働力の提供形態には請負と派遣がある。
請負とは、仕事を外部の企業に依頼して、成果物に対してお金を支払う労働契約のこと。社員の指揮命令権は発注先にあり、発注元は口出しをすることができない。
派遣とは、人材派遣会社に依頼して、自社に人材を派遣してもらう労働契約のこと。社員の指揮命令権は発注元にある。
Capter14-5「関連法規いろいろ」
知的財産権は大きくわけると著作権と産業財産権の2種類。
著作権とは、著作物に対する権利を保護するもので、創作された時点で自動的に権利が発生する。著作権の中には、著作人格権と著作財産権があり、著作人格権は著作物の生みの親に付与される権利で他人に譲渡したり、相続したりすることはできず、著作財産権は、著作物から発生する財産的権利で、他人に譲渡したり、相続したりうすることができる。
産業財産権とは発明や意匠(デザイン)に関する権利を保護するもの。産業財産権は先願主義があり、発明しただけでは自動的に権利は発生せず、特許庁に登録することで、はじめて権利が発生して保護対象となる。
産業財産権には特許権、実用新案権、意匠権、商標権などがある。
法人著作権とは、法人に著作権を与えること。法人の発意に基づく法人名義の著作物の場合、特段の取り決めがない限り、制作担当者が作ったものでも、雇っていた法人に著作権が帰属することになる。
製造物責任法(PL法)とは、製造物の欠陥によって消費者が生命、身体、または財産に損害を負った場合に、製造業者等の追うべき損害賠償責任を定めた法律のこと。この法律に則って賠償責任を求めるには、損害と欠陥の因果関係が立証される必要がある。
不正アクセス禁止法とは、不正なアクセスを禁止するための法律のこと。
具体的には、
・他人のIDやパスワードを盗用して、システムを利用可能とする行為
・不正な手段によってネットワークのアクセス認証を突破してシステムを利用可能とする行為
・セキュリティホールをつくなどによってシステムを不正に利用可能とする行為
・不正アクセスを助長する行為
などが該当する。
感想・気づき・つまづいた点
いちばんやさしいITパスポートでも学んだ範囲なので、企業活動と関連法規の範囲であれば、問題なく点が取れそうな気がします。
ただ、全くわからない分析手法や法律が出てきた場合、完全にお手上げになってしまう可能性はあると思うので、そこだけは注意が必要かなと思います。
あとは過去問で、組織形態の出題パターン、不正アクセス禁止法の出題パターンを学べば、完璧になるのではないか?と信じて本番に挑みたいと思います。
明日の予定
今日はChapter14企業活動と関連法規が無事に終了しました!
明日からはChapter15経営戦略のための業務改善と分析手法に突入します。
明日の目標はChapter15-1PDCAサイクルとデータ整理技法~Chapter15-3QC七つ道具と呼ばれる品質管理手法たちを終わらせたいと思います。
ITパスポート試験まで残り5日。
明日も勉強がんばります。



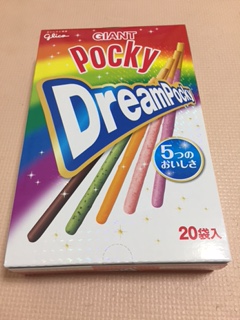





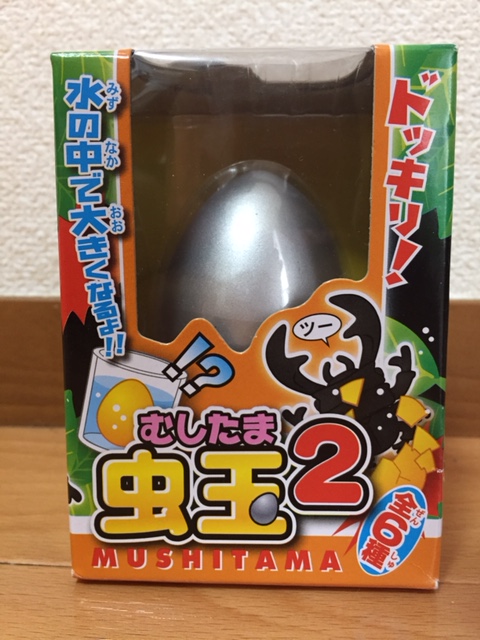


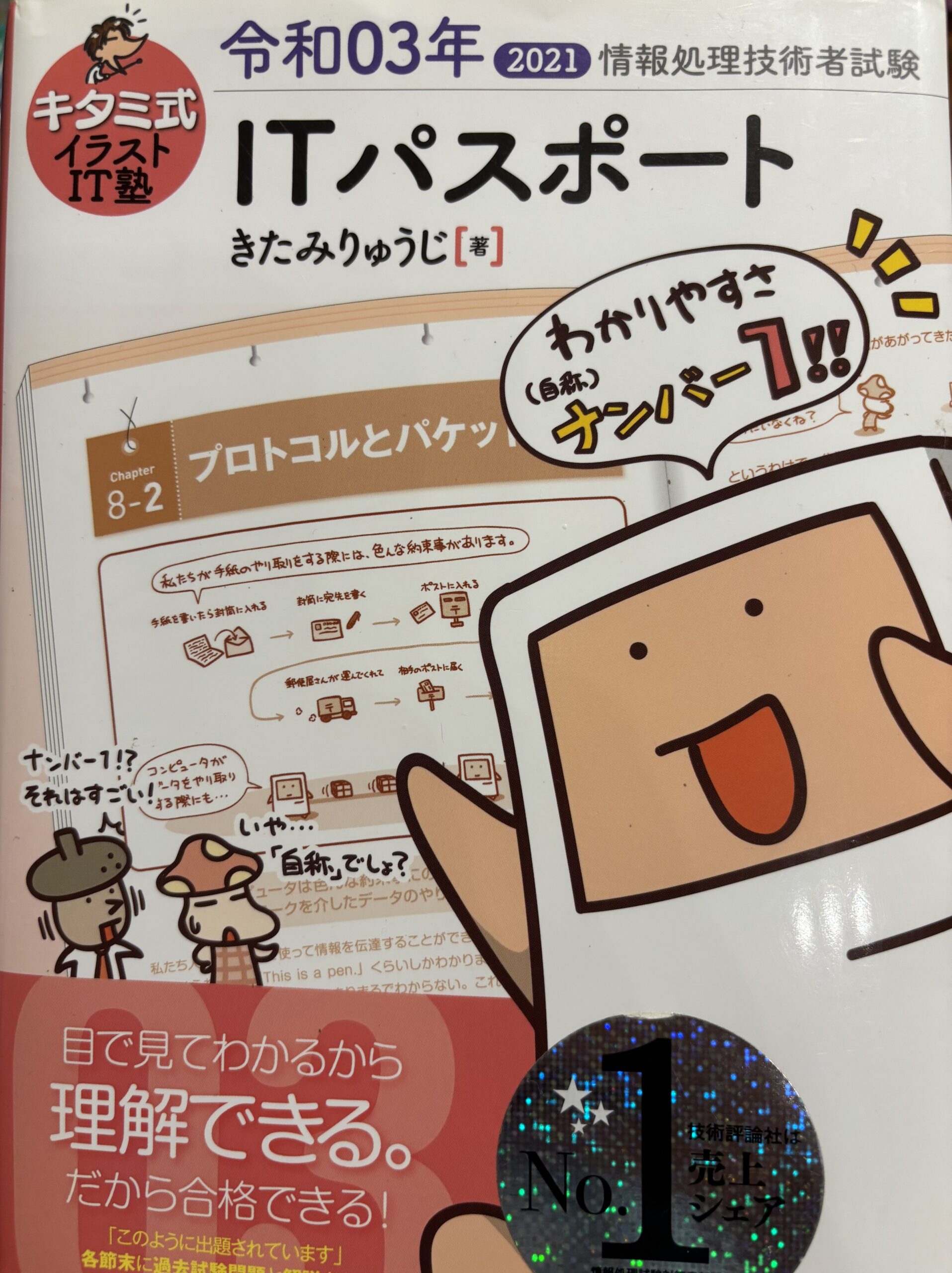

コメント